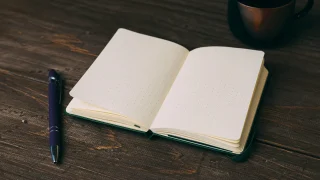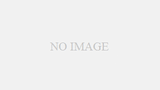民法等の一部を改正する法律は令和6年5月24日に公布、2年以内の政令で定める日から施行される予定になっています。
福岡県行政書士会の市民法務部の活動として、この改正のレポートを纏めることになったのですが、調べる中で法定養育費の発生と共同親権申立てについて、改正施行前後で離婚した場合に差があることがわかりました。この点について疑問を持っているので、今回記事にしてみました。
親権・養育費・親子交流に関する民法等改正に関する法務省のパンフレットには以下のような記載があります。
①法定養育費の規定は、本改正施行後に離婚したケースのみ適用される
②共同親権は、改正前に離婚したものでも、単独親権から共同親権への変更を申し立てることができる(意訳)
①は該当する新民法766条の3が新設されるのに伴い、法の不遡及の原則が絡んで、本改正施行後に離婚したケースのみ適用されるとしていると考えています。②は新民法819条6項において、現行民法の819条6項を流用しており、法の不遡及に当たらないと判断され、申立てをできるのではないかと考えています。
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
新民法766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし書き略
(離婚又は認知の場合の親権者)
新民法819条6項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる
※新民法819条は7・8項が追加されたりと変更が加えられている
理屈上は差が生まれることは理解できるのですが、本改正は、養育費の低調な受給率が要因となって進められたという経緯があります。そのためどうしても、法定養育費の規定が本改正施行後に離婚したケースのみ適用されるという内容が腑に落ちないのです。
改正法施行前の人に対し、何かしらの救済措置がないか、本当に法の不遡及の原則が絡んで差が生まれているかなど改正家族法の研修を受けているので、機会があれば尋ねてみたいと思います。
この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考される場合は、詳細な検討をお願いします。