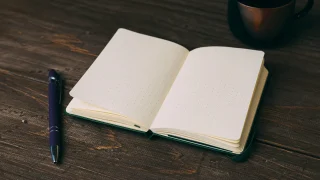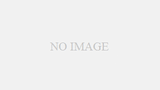遺言と家族信託の特徴を知ることで、どちらかを選択または両者の併用という考えを生み出すことができます。
まず遺言は、作るのも破棄(変更)するのも、本人独りで自己完結できることが強みであると考えます。つまりそれは、自分自身が築き上げてきた財産を亡くなるまでコントロールできるということにもつながります。
対して家族信託は、本人以外にも信託を実行する人が必ず想定されています。
信託は実行する人が存在するため、まず本人と信託実行者の合意がないと信託が成り立ちません。さらに不動産が信託財産に入っていたとすると信託登記を行うので、仮に登記を取り消すとしたら登録免許税は無駄になってしまいます。
遺言も家族信託も、認知症気味の妻を心配し、子供たちに後事を託す形のものを作ることがあると思います。
家族信託であれば、信託実行者に対して監督人(親族や家族信託の作成に携わった専門職等)を法的に組み込むことが可能です。対して遺言は負担付き(財産を譲り渡す代わりに妻の世話をするよう指示する)遺言が行われたとしても、それを監督する人を選任する仕組みはありません。敷いていえば他の相続人が監督人ということになります。
遺言と家族信託を併用する有効な場面も考えてみましょう。
父と母がいて、子供(長男・長女)が2人いる。ただ長女の方は10数年所在不明で、連絡がつかない状態となっているとします。そして父名義の財産は土地と家で2000万、預貯金2500万あったとします。
土地と家は母(妻)に残したいと考えており、長男も同意しています。
そこで父は土地と家を母に相続させる遺言を作成しました。これによって父が亡くなっても、相続人間で遺産分割協議書を作成せず、土地と家を母の名義にすることができる手段を作れたことになります。(仮に遺言がないとすると、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てるなど、かなりの手間と労力が必要になることにも注意が必要です)
ただ懸念としては所在不明の長女のことです。連絡がつかない状態が長いとはいえ、どこかで暮らしているのかもしれない。相続人には父の遺産をもらう権利があり、それは法定相続分の1/2と決まっています。今回の総財産は4500万かつ3名の相続人を想定しているので、1人当たり1500万の1/2、長女は相続時の権利として750万を主張することができます。これを遺留分と言います。
父はこの遺留分対策として、750万の預貯金を信託財産とする家族信託を作ることにしました。
遺留分は、被相続人 今回の場合は父が亡くなったことを長女が知った(相続開始を知った)時から1年、もしくは父が亡くなったときから10年経過した時は、その権利が失われます。
1年の方の対策としては、長女の所在がわかっていた最新の場所に、遺言と父の死亡を知らせる内容の書類を内容証明で送ることなどが考えられます。
次は遺留分の10年経過について考えていきます。父が亡くなってから10年で長女の遺留分の権利が消滅しますが、正直10年というのは長い時間です。その間に母の認知能力が低下する可能性もあります。その対策として今回は家族信託を作ったわけです。仮に権利消滅の経過途中で長女が見つかって遺留分を主張してきたときも、長男は家族信託の条項を基に、1人で対応可能です。そういう家族信託を今回は作っていました。
遺言も家族信託も、置かれた状況により有効な場面が異なります。情報を収集しつつ、分からない場面が出てきたら専門家への相談も視野に入れてはいかがでしょうか。
もしご自身で作られるなら、家族信託と比べて比較的難度の低い自筆証書遺言からの作成をお勧めします。法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度も始まっていますので、遺言の保管においてもメリットがあります。
この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考される場合は、詳細な検討をお願いします。