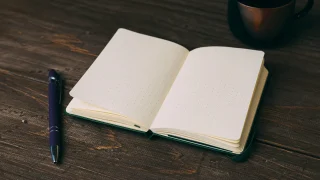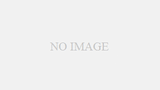まず祭祀継承というのは、一般的なことを言うと仏壇やお墓の管理をする人を決めるというものです。
祭祀継承を行わず一代限りにする墓じまいが徐々に増えてきていますが、全体としては祭祀継承を行う方が多いでしょう。しかし墓の管理等にはお金が時間がかかり、相続した兄弟同士で押し付け合いが発生する場合があるのもまた事実です。祭祀継承問題が大きくなりすぎ、相続が宙ぶらりんになるということも考えられます。
祭祀継承はプライベートの分野の深層部分に触れるものなので、兄妹間でこじれると相談できるところすらどこに行えばよいか分からないと思います。その答えとして調停のことをお話します。
調停とは裁判所が用意した仲介(調停委員会)を通した話し合いです。話し合いなので当事者の折り合いがつかなければ不成立なのですが、調停で行える「祭祀の承継者の指定」は、成立しなければ審判(似裁判)によって承継者が指定されます。審判になると決定するのは裁判官なので、思い通りに事が運ぶ保証はありませんが、「祭祀の承継者の指定」については決着することになります。なお調停の途中で申立てを取り下げることはできます。
では実際、「祭祀の承継者の指定」の調停は行われているのでしょうか。
最高裁判所が公開している令和2年度 家事調停事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所を見てみると、「祭祀の承継者の指定」は261件あります。
「祭祀の承継者の指定」は、「養育費の請求」や「婚姻費用(別居時の離婚するまでの生活費)の分担」といった【これ決めてないと後で絶対揉める】といったものと同じで、別表第二という分類に属します。別表第二は調停が不成立になると、審判に必ず移行します。
上記の資料によると令和2年の別表第二調停事件総数は124724。261/124724で総数の約2%しか行われていません。令和2年の家事調停(離婚・遺産分割等)総数が上記資料によると201550なので、調停全体でみると「祭祀の承継者の指定」は1%程度しかありません。
ちなみに「祭祀の承継者の指定」の261件のうち、調停成立が48件、不成立が37件、取り下げが17件、調停に代わる審判(裁判官が少し調整すれば、調停成立するような感じのもの。当事者・裁判所共に負担が減るので、この方法にしましょうという提案的なもの)33件。調停が続いているのが114件で、調停に代わる審判に異議申し立てをしたのが4件。その他はこまごまとした内容になっています。
拗れてしまった祭祀継承問題の打開策として、調停を利用するのは有りなのではないかと考えられます。また相続人同士で祭祀承継の話し合いを行う上でも、調停という次の手段を知って挑むことで、踏み込んだ話ができるようになる可能性も生まれてきます。
祭祀承継の指定の調停は、調停が成立しなければ審判に必ず移行しますが、裁判所はこの問題に対してどのように考えているのでしょうか。これについては、1つの判例が指針になると考えられます。
「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経過、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を統合して判断すべき」で、「祖先の祭祀は・・・死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活・親和関係にあって、被相続人に対し前記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である」(東京高決平成18年4月19日判夕1239号289頁)
調停の申立てもネットで調べられますし、分からないところは家庭裁判所に聞けばいいだけです。
なお申立てを行う裁判所は、相続開始時(被相続人<財産を持って亡くなった方>の住所地)の家庭裁判所であることも留意して頂ければと思います。管轄に関しては生成AIに尋ねてみるのが、ネットサーフィンで調べるより速いと思います。
この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考にされる場合は、詳細な検討をお願いします。