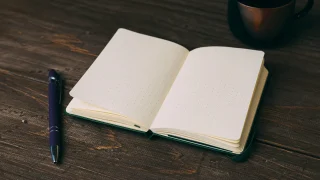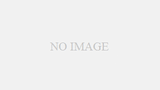今回の遺言書には、配偶者居住権という民法で定められた権利を使います。
これが必要になったり有効に働くのは、子供に土地と家の所有権を(配偶者の認知症対策等で)相続させた上で、配偶者に自宅を使い続ける権利を保障したいときなどです。つまり配偶者に残った全ての財産を相続させるというときにおいては、この遺言の文言は必要ありませんので、ご注意ください。
第1条 遺言者(〇〇〇〇)は、自宅(である目録記載の建物)の配偶者居住権を遺言者の妻昭子(昭和〇〇年〇月〇日生)に遺贈する。
2 前項の配偶者居住権の存続期間は、妻昭子の死亡の時までとする。
第2条 遺言者は、自宅不動産(土地及び建物)前条の負担に付きにて長女〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、第1条の配偶者居住権に関する遺言執行者として妻昭子を指定し、同権利に関する登記手続きなど第1条の遺言を執行させるための権限を与える。
第3条の意図は以下の通りです。配偶者居住権は登記することができます。登記をすると配偶者が第三者に対抗することができます。例えば子供が借金の方に自宅を売った時でも、配偶者居住権が登記されていれば配偶者は自宅に住み続けることが可能となります。故に遺言執行者を指定して、(他の相続人の協力が無いときでも)登記手続きができるようにしているわけです。
話はかわり、配偶者居住権も相続分として計算され、配偶者の相続分が目減りする可能性があります。それを防ぐのが民法903条第3項の持戻し免除です。婚姻期間が20年以上の夫婦間で配偶者居住権が遺贈された場合も、持戻し免除の意思表示があったものと推定されるとされています(民法1028条3項、903条4項準用)が、遺言で明確にしておくと安心です。それを踏まえた遺言をこれから書いていきます。
第4条 遺言者は、第1条にて妻昭子に自宅建物の配偶者居住権を遺贈したが、これは妻が共働きで遺言者と協力して自宅不動産を購入したことを踏まえたもので、遺言者の死亡後も妻が自宅建物内で安心して生活できることを保障するためのものであることから、民法903条1項で規定する相続財産の算定に当たっては、上記遺贈による配偶者居住権の価値は、相続財産の価額に加えないとの意思表示をする。
民法1028条(配偶者居住権)
①被相続人【本人】の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
1.遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
2.配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
②居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
③第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考される場合は、詳細な検討をお願いします。