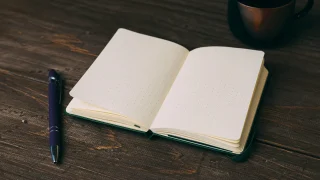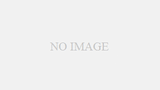家族信託とは商標登録された言葉で、本当は民事信託というのですが、ここでは家族信託と書いていきます。
委託者・受託者・受益者など家族信託の基礎知識があることを前提にお話ししますので、その点はご留意下さい。
結論から言うと、家族信託は遺言や遺贈とは違うメリットがあるため、その有効性を活かす必要があるなら、家族信託を行うのが一番の解決策になります。
では家族信託の最大のメリットは何でしょうか。それは委託した次の者、次の世代など「先のことを考えて内容を組み立てることができる」ことにあると考えています。
家族信託が有益に働く、具体的な例を見ていきましょう。
父と母、そして息子1人いる3人世帯で、父が賃貸の不動産オーナーだったとします。父は少々足腰が弱くなっており、不動産オーナーの実質的な業務は息子がやっていました。父はいろんな情報から自分が認知症になってしまったら、大変なことになることは知っていました。また贈与が相続などの場合より税金がかかることも知っていました。
そこで新たに知った制度が家族信託でした。家族信託は信託登記というものを行います。委託者(父)・受託者(息子)・受益者(父)の信託登記により、家族信託における「財産分離機能」が発生し、家族信託で条項を定めていれば、父が意思決定が難しい認知症になった後でも、父の財産から不動産の大規模修繕行ったり、売却などが可能となってきます。
なお家族信託の条項というのが「考案を要する書類」となり、内容がオーダーメイドになり作成難度が高く、作成する側として相当な責任を負うため、遺言などより高額な報酬となっているのが一般的になっています。
もう一つ例をあげていきます。
父と母がいて、兄と妹がいる。兄には嫁がいて、妹は寝たきりの障害者だった。兄と妹の仲は良く、父と母から兄に対し、「私たちがどうにかなった後は、妹のことを頼む」と言付かっており、兄も了承していました。しかし父と母は、兄が妹より先になくなった後のことを心配していました。実はこの両親には今は亡き子(長男)がいて、人はいつ死ぬか分からないという観念をもっていたためです。
例えば負担付き遺言で、妹のことをお願いしていたとしても、兄が妹より先になくなってしまうと、兄が受け継いだ財産は制限なく兄の嫁やその子供たちに受け継がれます。兄嫁が妹の面倒をみてくれるかは不透明です。
ここで解決策となるのが家族信託となります。家族信託は契約なので、兄が妹より先に亡くなったときに、妹の世話をするのが兄の嫁と設定することも可能なのです。血のつながりはないわけですからそれに甘えることはできず、資質や関係性、妹の世話を行う報酬など様々なことを考慮に入れる必要はありますが、家族信託は遺言にできないことを実現可能ということになります。
私は家族信託を遺言を越えるような魔法(仕組み)ではなく、贈与・遺言・遺贈などを含めた選択肢一つだと捉えています。
日弁連信託ガイドラインでも似たような考え方を示されており、民事信託を一通り勉強した方は、自らの考えを固めるためにも一読しておくとよいかもしれません。
元来信託法とは、社会ニーズを拾い上げるために生み出されてきたという歴史的な背景があります。例えば、信託法の起源の1つとされるローマ法においては、以下のようなことがありました。
紀元前169年、ローマの護民官ヴォコニウスは、10万セステルティウス以上の財産を持つ者の相続人に対し、女性の相続権や遺贈を受ける権利を法で剥奪しました。しかし、妻や娘に財産を残したいという想い(ニーズ)は存在し続けました。結果として、第三者の男性に一旦遺贈した上で、妻や娘に財産を移譲するという仕組みが生み出されました。
現代でも贈与や遺言、遺贈などでは賄いきれないニーズがあることは周知の事実です。そのニーズを埋めるために2007年に改正信託法が施行されたと考えると、改正に携わった者の意図するところが見え、遺留分など未だ判例がなく決着がつかない解釈論において、1つの指針が己の中で生まれるかもしれません。
この記事は執筆当時の法律等に基づき作成されておりますが、完全性や正確性を保障するものではありません。記事の内容を参考にされる場合は、詳細な検討をお願いします。